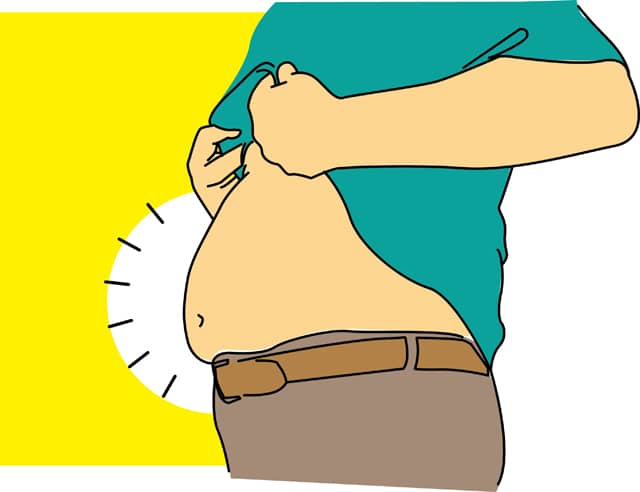 肥満と健康の関係をテーマとするテレビ番組や雑誌・新聞の記事を目にしない日はないといえるほど、肥満と健康の関係は、現代日本人にとって大きな関心事となっています。
肥満と健康の関係をテーマとするテレビ番組や雑誌・新聞の記事を目にしない日はないといえるほど、肥満と健康の関係は、現代日本人にとって大きな関心事となっています。
とくに近年の食生活の欧米化や運動不足などが原因となって急増していることは社会問題となっていて、健康を維持するための肥満にならない予防法や解消方法が、医学会、行政、メディアなどの多くの場で議論されています。
本記事では肥満とは何か、肥満の要因、肥満と病気の関係性、これらのテーマについてお話を進めていきます。
(関連リンク)
肥満、肥満症、メタボリックシンドローム
肥満と体脂肪の関係について
注意しよう 危険な内臓脂肪型肥満
肥満とはなにか? 肥満の定義
肥満とは、ただ「体重が重い」や「太っている」ということではなく、体脂肪が過剰に蓄積した状態のことです。体脂肪とは、身体に蓄積される脂肪の量のこと。過剰に蓄積されると肥満の原因になることがあります。一方でエネルギーの蓄えとして働いたり、内臓を守ったり、体温を保ったりする役割があります。
肥満を定義する1つの方法に、BMI(Body Mass Index)という計算方法があります。
「体重÷身長÷身長=BMI」この計算式で身長に対しての体重の比率が産出され、肥満度合いが判定できます。
日本人の場合、BMI25以上が肥満とされています。BMIが25以上を超えたときから生活習慣病などの症状が増えることが分かっています。
さらにBMIが35以上になると高度肥満に区分されます。
BMIの計算方法
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
例:体重60㎏で身長160㎝の場合
60÷1.6÷1.6=23.4
BMI=23.4
肥満になる要因とは?
複数の要因が重なって肥満になると考えられています。以下の要因が主なものとして挙げられます。
-
食生活の変化:現代日本人の食事に多く登場する高カロリーで加工された食品やファストフードなどの食品には、多量の糖分、脂肪、塩分が含まれているため、過剰に摂取すると肥満につながる。
-
運動不足:運動不足はエネルギーの消費が減少するため、肥満の原因となる。現代社会の便利なテクノロジーは移動や作業を手軽にすることができるため、運動不足に陥る傾向がある。
-
ストレス:現代社会では高いストレス状態に陥りやすい環境があるため、ストレスによる過食や不規則な生活習慣が肥満の原因になることも。
-
遺伝的要因:遺伝的な要因も肥満の原因の1つ。親が肥満であれば、子供も肥満になりやすい傾向がある。
-
環境的要因:家族の食生活や生活環境、社会環境によっても、健康的な食習慣を維持することが難しい場合があり肥満の原因になることがある。
肥満と病気の関係
肥満は様々な病気やけがの要因となります。とくに、肥満が要因となる糖尿病や高血圧などの生活習慣病が悪化して、血管が傷ついたり脆くなったりする動脈硬化に至るケースでは、心筋梗塞や脳卒中などの命に関わる危険な心血管イベントがおきるリスクが高まります。
肥満が原因でおきる病気やけがには、以下のようなものがあります。以下に挙げたもの以外では、高尿酸血症からの痛風、脂肪肝やすい炎の促進、大腸がんや前立腺がん、乳がん、子宮がんなどの多くのがんのリスクを高めることも指摘されています。
-
糖尿病:肥満はインスリンの分泌や効果が低下し糖尿病のリスクを高める。高血糖によって眼病、腎病、神経障害、心臓病などに合併することがある。
-
高血圧:肥満は動脈硬化を促進し高血圧の原因となる。高血圧は心臓病や脳卒中などの心血管イベントリスクを高める。
-
高脂血症:肥満はコレステロールや中性脂肪の増加を招き高脂血症の原因となる。高脂血症は動脈硬化を促進し、心臓病や脳卒中などの心血管イベントリスクを高める。
-
非アルコール性脂肪性肝疾患:肥満により肝臓に脂肪が蓄積されれば非アルコール性脂肪性肝疾患から肝炎が生じることも。非アルコール性脂肪性肝疾患は肝硬変や肝臓がんのリスクを高める。
-
呼吸器疾患:肥満は肥満性肺炎や睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患を引き起こすことがある。
-
体重増加による障害やけが:筋肉量や骨量が減った高齢者が肥満の場合、骨や関節への負担が大きくなるため、腰痛や膝痛などの関節障害、転倒によるけががおこりやすくなる。