概日リズム睡眠障害は、体内時計(生体リズム)の乱れによって、睡眠と覚醒のリズムが社会的な生活時間と合わなくなる病気です。
夜眠れない、朝起きられないといった不眠症状とは異なり、「眠ることはできるが、眠る時間帯がずれてしまう」点が特徴です。
現代社会では、夜遅くまでのスマートフォン使用や夜勤・交代勤務などによって、体内時計が乱れやすくなっており、患者様は若年層から高齢者まで幅広い年代にみられるようになっています。
概日リズム睡眠障害は、「眠れない病気」ではなく「眠る時間がずれる病気」です。
無理に生活を合わせようとすると、強い眠気や体調不良、抑うつ気分などを引き起こすことがあります。
生活リズムを整えることで改善が期待できるため、症状が続く場合は医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

(関連リンク)
不眠症 ~寝付けない 中途で目が覚める 熟睡できない~
不眠症の薬を使わない治療法(非薬物治療)について
不眠症の薬を使う治療(薬物治療)に使われる西洋医薬と漢方薬
概日リズムと睡眠の仕組み
人の体には、約24時間の周期で体温やホルモン分泌などを調整する「概日リズム(サーカディアンリズム)」が備わっています。
このリズムは、脳の視交叉上核(しこうさじょうかく)という部位にある「体内時計」によって制御されており、外界の明暗(光)を手がかりに調整されています。
夜になると脳から「メラトニン」という睡眠ホルモンが分泌され、自然な眠気が誘発されます。
しかし、夜遅くまで明るい光の部屋の中で過ごしていたり、生活リズムが不規則な生活を続けると、体内時計の働きが乱れ、睡眠時間のずれを引き起こします。これが概日リズム睡眠障害です。
概日リズム睡眠障害のタイプとおもな症状
概日リズム睡眠障害の特徴は、睡眠時間帯のずれです。
本人は十分な睡眠時間を取っているつもりでも、社会生活とリズムが合わないため、学校や仕事などの日常生活において支障をきたすことがあります。
- 睡眠覚醒相後退症候群:夜遅くまで眠れず、朝起きられない。
- 睡眠覚醒相前進症候群:夕方早く眠くなり、早朝に目覚めてしまう。
- 交代勤務障害・シフトワーク障害:夜勤やシフト勤務により生活リズムが崩れる。
- 非24時間睡眠覚醒症候群:日ごとに少しずつ睡眠時間が遅れていく。
- 旅行などで起こる一時的な時差ボケも一種のリズム障害。
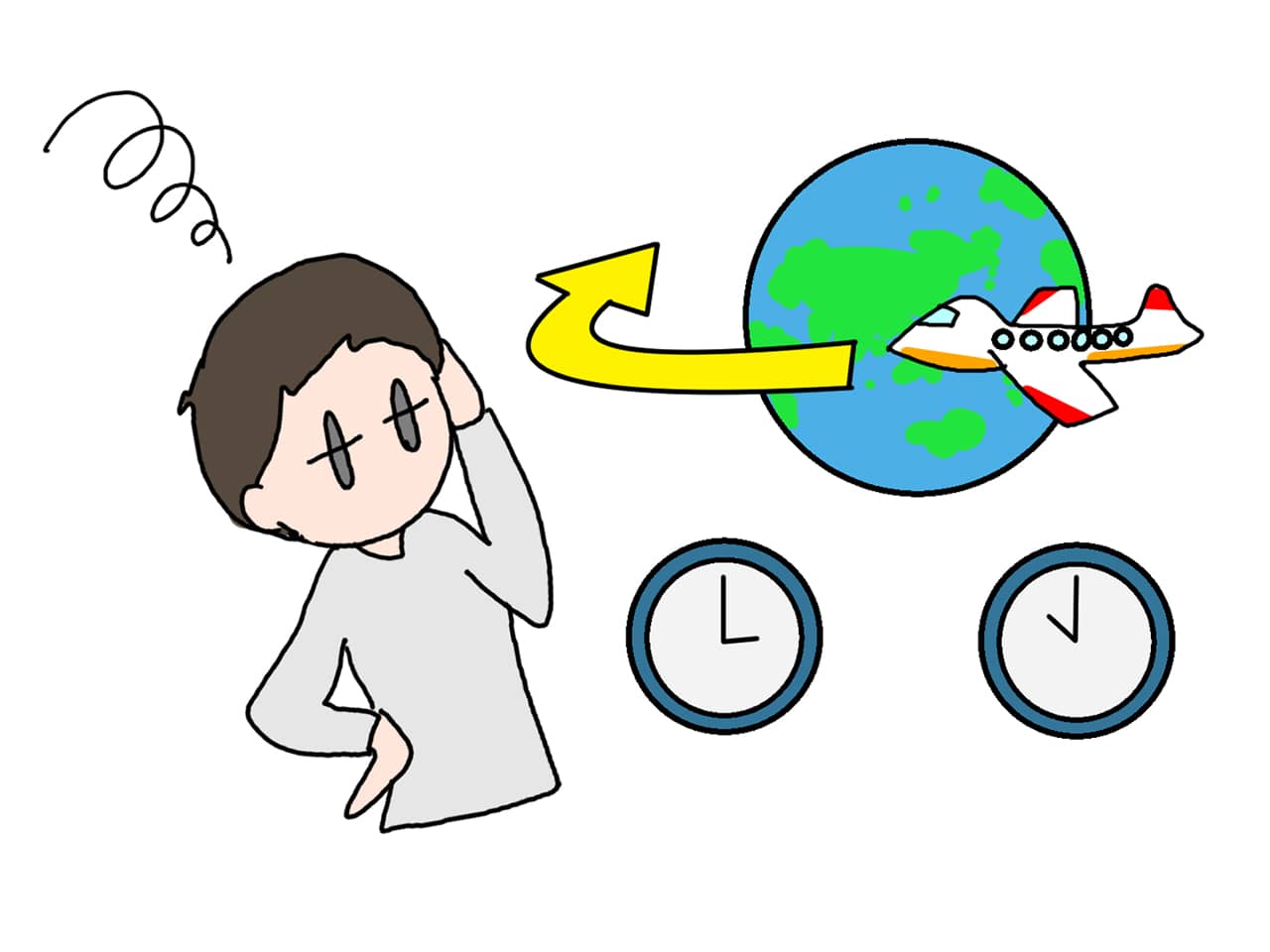
若年層では「朝起きられない」「学校に行けない」といった形で発症することが多く、高齢者では「夕方から強い眠気が出る」「早朝に目覚める」などの訴えがみられます。
日中の強い眠気や集中力の低下が続くと、うつ症状のような精神的不調を伴うこともあります。
概日リズム睡眠障害の診断
診断の基本は、問診時に患者様の生活リズムを確認することです。「何時に寝て、何時に起きるか」を数週間記録した「睡眠日誌」や「睡眠ログ(アクチグラフ:活動量計)」などをもとに評価します。
必要に応じて、脳疾患(認知症・脳炎など)の除外のためにCTやMRI検査を行うこともあります。また、専門医療機関では脳波やホルモン分泌のリズムを調べる精密検査が行われる場合もあります。
概日リズム睡眠障害の治療は生活リズムの調整
治療の基本は、生活リズムの調整です。体内時計を「正しい時間」に戻すことを目指します。生活習慣の改善以外の治療法として、薬物療法や光療法があります。
生活習慣の改善
- 朝起きたら朝日を浴びる(光が体内時計をリセットします)。
- 昼間は適度な運動を行う。
- 寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控える(ブルーライトを避ける)。
- カフェインやアルコールを控え、静かな環境で就寝する。
- 就寝1時間前の入浴など、リラックスできる習慣を取り入れる。

- 薬物療法
- 必要に応じて、体内時計を調整する薬(メラトニン製剤やメラトニン受容体作動薬「ロゼレム」など)が処方されます。
ロゼレムは、予定睡眠時間の3〜5時間前に服用することで、眠気のリズムを整える効果があります。
一般的な睡眠薬(ベンゾジアゼピン系など)は、この疾患にはあまり用いられません。 - 光療法(高照度光療法)
- 朝の一定時間、2500〜3000ルクス程度の明るい光を浴びる治療です。
遅れているリズムを早めたり、早すぎるリズムを遅らせるなど、タイプに応じて照射時間を調整します。自宅で行うことも可能で、医師の指導のもと実施されます。
概日リズム睡眠障害の予防と生活の工夫
概日リズム睡眠障害は、日常生活の工夫で改善・予防が可能です。
- 就寝・起床時刻を毎日なるべく一定に保つ。
- 朝日を浴び、夜は部屋を暗くする。
- 休日でも睡眠リズムを大きくずらさない。
- 夜勤や交代勤務がある場合は、光環境を工夫し体内時計を調整する。