日本人の場合、BMI25以上が肥満とされています。BMIが25を超えたときから生活習慣病などの症状が増えることが分かっています。肥満になると、糖尿病や脂質異常症・高血圧症・心血管疾患などの生活習慣病をはじめとして数多くの疾患のもととなるため、健康づくりにおいて肥満の予防・対策はとても重要です。
今回の栄養部の記事では、肥満予防のためのダイエットを食生活改善中心にご紹介します。
肥満かどうかを判断する基準となるのは体格指数(BMI)
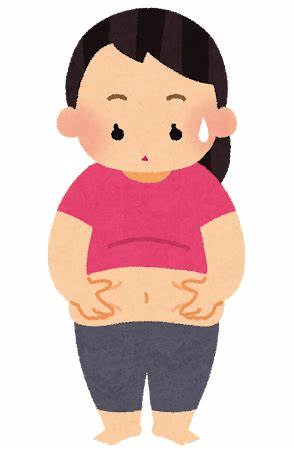 「体重が増えた」「お腹の脂肪が気になる」などと太っていることを気にする方が近年増えています。
「体重が増えた」「お腹の脂肪が気になる」などと太っていることを気にする方が近年増えています。
肥満とは、身長に対して体重が重い状態のことを指します。肥満かどうかを判断する基準となるのは体格指数(BMI)です。
日本人の場合、BMI25以上が肥満とされています。BMIが25を超えたときから生活習慣病などの症状が増えることが分かっています。
さらにBMIが35以上になると高度肥満に区分されます。
BMIの計算方法
自身の身長と体重を当てはめ、BMIがどのくらいなのか計算してみましょう!
BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
例:体重60㎏で身長160㎝の場合
60÷1.6÷1.6=23.4
BMI=23.4
肥満予防のためのダイエットの基本は食生活改善、有酸素運動、毎日の体重計測
肥満予防のためのダイエットの基本は食生活改善、有酸素運動、毎日の体重計測の3つ。
有酸素運動がおすすめです。有酸素運動とは筋肉への負荷が比較的軽い運動のことで、20分くらいから脂肪の燃焼効果がアップするといわれています。ウォーキングやジョギング、サイクリングなどが該当します。
2〜3日に1回の頻度でも継続することでダイエットに役立ちます。
毎日体重計測を行えば、自分の体重増減を常に意識するため体重管理に有効です。
肥満予防のためのダイエットには食生活改善が大事!
肥満を予防するのに基本的な食生活改善は?
- 夜間に食べ過ぎないようにする
- 1日3食、規則正しく食べる
- ゆっくりよく噛んで、食事に時間をかける
- アルコールは適量に
たんぱく質を十分に摂取する
一般的な成人が1日にとるべきたんぱく質の量は、標準体重(身長(m)×身長(m)×22)の1kgあたり1.0〜1.2gとされています。肉類のほか、魚類や、卵、乳製品などに多いので、意識して摂取してください。
糖質の摂取量を減らす
朝、昼、晩の三食で、米やパンなどの主食や果物の摂取を制限します。1日の糖質を150~200g以下におさえましょう。また、糖質の消化スピードを緩やかにし吸収されにくくするために、「食事はゆっくりと味わいながら」を意識し、1口で30回ほど噛むように心がけましょう。
GI値が低い食品を選ぶ
血糖値が急上昇するとインスリンが過剰に分泌され、血糖値の乱高下や肥満につながります。低GI食品は、糖質が体内で消化吸収されるまでに時間がかかるのが特徴です。食後の血糖値がゆっくりと上昇するため、インスリンの過剰な分泌を抑えられます。

脂質の摂取量を減らす
食材を選ぶときには、青魚やごま油、オリーブ油など「不飽和脂肪酸」が多く含まれている食材を選ぶようにしましょう。肉やバター、生クリームなどに含まれている「飽和脂肪酸」と同じ脂質ではありますが、脂肪への変わりやすさに違いがあります。魚中心の食生活など「体にいい油」を摂りましょう。「茹で」「蒸す」といった油を使わない調理法がおすすめです。
食物繊維を十分に摂取する
よく知られている便秘の解消以外にも「コレステロールの吸収を防ぐ」役割があります。水溶性食物繊維は、コレステロールの腸での吸収を防ぎ、体外に排出する働きがあります。食物繊維が多く含まれている、きのこ類、野菜類、海藻類を積極的に食べるようにしましょう。
ビタミンやミネラルを十分に摂取する
エネルギー代謝の促進、免疫機能の維持、骨の健康維持、美肌効果、精神的健康のサポートなど、ビタミンは多くの重要な役割を果たしています。ダイエット中はビタミン不足になりがちです。ビタミンが不足すると痩せにくい体になってしまいます。
文責:管理栄養士 鶏尾紗季