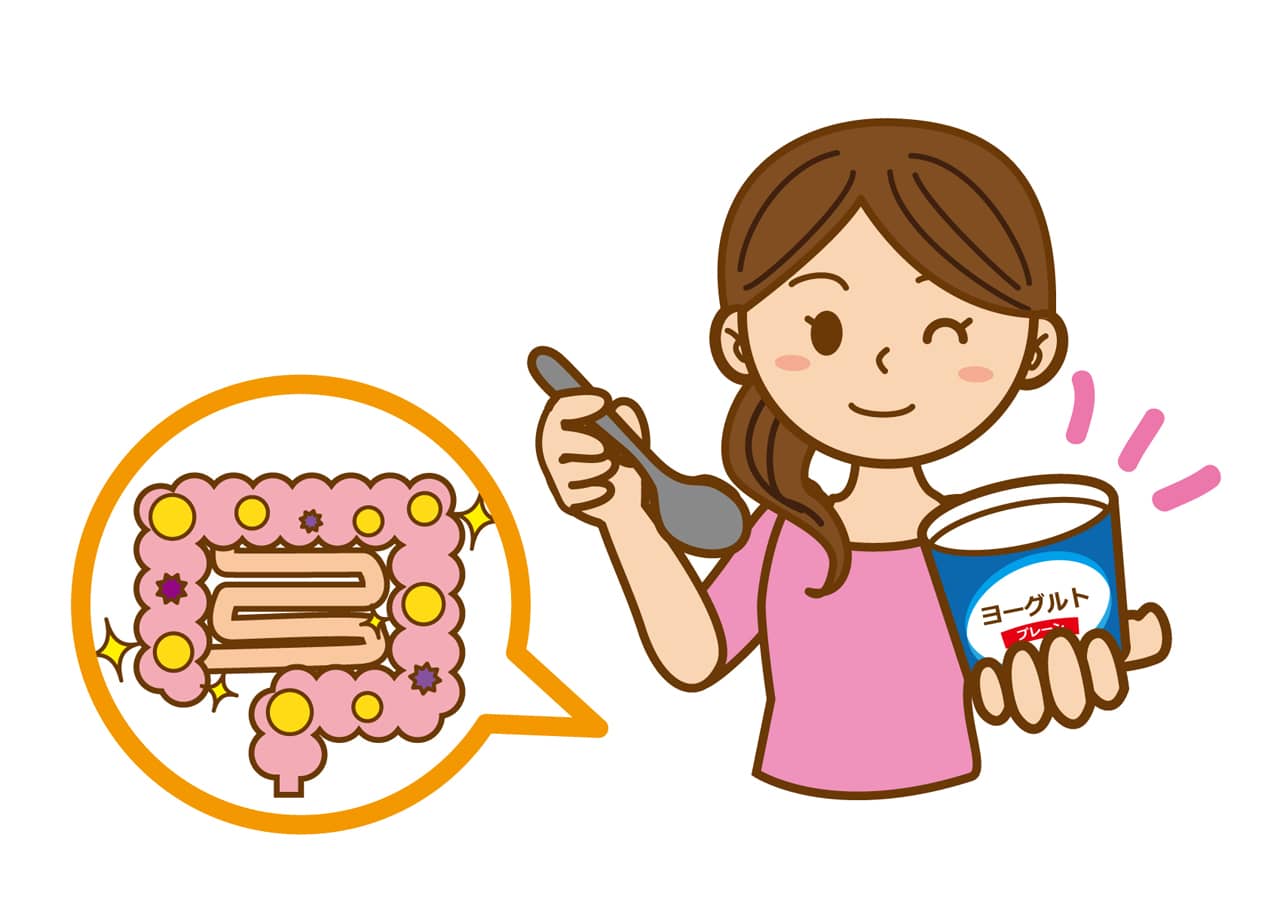下痢・軟便は、多くの方が一度は経験する消化器症状です。一時的な不調であることも多いですが、中には病気が隠れているケースもあり、適切な診断と対処が重要になります。
下痢・軟便は、多くの方が一度は経験する消化器症状です。一時的な不調であることも多いですが、中には病気が隠れているケースもあり、適切な診断と対処が重要になります。
この記事では、下痢・軟便の病院での診断方法、治療法、そして日常生活での予防法について詳しく解説します。
下痢・軟便の症状は、「薬物療法」と「生活習慣・体質改善」の両面からアプローチすることで、症状が緩和しやすくなります。
急性症状には医薬品や漢方薬による対応を、慢性症状や予防には食事・運動・ストレス管理、そして腸内環境の改善を意識することや自分にあった漢方薬などで体質改善をはかることが大切です。ご自身の体質や症状タイプに合わせて、適切な対策を取り入れることで、健やかな腸を目指しましょう。
関連リンク
下痢と軟便:定義・メカニズム・タイプ・原因・症状・病院診察を受けるべき症状について
下痢・軟便の検査と診断
患者様が下痢・軟便を訴えて病院を受診された際には、まず詳細な問診と診察をしたのち、下痢・軟便の原因を確認するための検査を行ないます。
診察や検査を通じて、「水分やアルコール、乳製品や人工甘味料製品などの摂取過多による単純な下痢」なのか、それとも「何らかの病気が原因の下痢」なのかを区別することが重要です。また、重症度も評価され、脱水症状がひどい場合は緊急性が高く、迅速な診断と点滴などの治療が必要となります。
問診
- 便の性状と発症時期:
軟便の程度や、いつから症状が出始めたかを確認します。 - 食事内容:
食中毒の可能性を探るため、前日の食事内容について詳しく伺います。 - アレルギーの有無:
牛乳や人工甘味料などによる過敏症の有無も確認します。 - その他の情報:
アルコールの摂取状況、海外渡航歴、発熱や吐き気などの随伴症状、腹痛の有無とその持続期間なども重要な情報です。
診察
- 腹部診察:
お腹を触診し、痛みの部位、腸の音(腸雑音)、腹膜炎の兆候がないかを確認します。 - 目の診察:
貧血の有無も視診で確認することがあります。
検査
症状に応じて、以下のような検査が行われます。
- 血液検査:
炎症反応(白血球やCRP)の確認が最も重要です。 - CT検査:
重症な場合や、より詳細な腹部の状態を評価する必要がある場合に行われることがあります。 - 便潜血検査:
慢性下痢や血便がある場合に、便に血液が混じっていないかを確認します。特に若い方や高齢者で血液が混じる場合は、潰瘍性大腸炎や虚血性大腸炎といった重篤な病気が隠れている可能性があり、非常に重要な検査です。 - 内視鏡検査:
出血の疑いがある場合や、他の検査で原因が特定できない場合に最終的に行われることがあります。 - 腹部レントゲン:
必要に応じて腸のガス像を確認します。
下痢・軟便の薬物療法
下痢・軟便の薬物治療には、西洋薬と漢方薬があります。患者様の下痢・軟便のタイプ(食中毒、ウイルス性、慢性など)を特定した上で、適切な薬が処方されます。
西洋医薬による下痢・軟便の薬物療法
西洋医薬による下痢・軟便治療の主なメリットは、即効性と原因に対する直接的なアプローチです。科学的根拠に基づいて開発された薬が多く、特定の症状や疾患に対して迅速な効果が期待できます。
- 整腸剤・乳酸菌製剤:
最も一般的に処方される薬で、乳酸菌などの成分が含まれている(例:ビオフェルミン、ミヤBMなど)。下痢により腸内細菌のバランスが崩れることがあるため、それを整える目的で処方される。善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌など)を補給し腸内環境を改善することで、慢性的な下痢や軟便の予防・改善が期待できる。 - 腸管運動抑制薬(ロペラミドなど):
腸の過剰な運動を抑え、便が腸内にとどまる時間を延長し水分吸収を促す。 - 収れん薬(タンニン酸アルブミン、次硝酸ビスマスなど):
腸粘膜の炎症や刺激を抑え、症状を緩和する効果がある。 - 吸着薬(天然ケイ酸アルミニウムなど):
過剰な水分や有害物質を吸着して排除する働きがある。 - 抗生物質:
細菌性腸炎と診断された場合に限り使用される。
漢方薬による下痢・軟便の薬物療法
漢方薬は、下痢を直接止める作用はあまり期待できませんが、お腹の痛みを緩和したり、腸の運動を整えたり、下痢症の体質を改善する目的で用いられます。急性期にも慢性期にも使われ、冷えやストレス、体質に合わせて選ぶことができます。
漢方薬の選択は、その時の症状や体質に適合するかどうかで判断されますので、専門家への相談が重要です。
- 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう):
食べ過ぎによる症状や、お腹の張り、軟便に対応。 - 五苓散(ごれいさん):
頭痛や口渇を伴う水様性の下痢、むくみに用いられ、体内の余分な水分を排出して調整し、水分代謝を整えることで下痢を改善する。 - 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう):
腹が張って痛む、排便困難な人向けで、腸管の緊張を緩和。 - 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう):
腹痛を伴うときに緩和目的で用いられる。
下痢・軟便 ~治療・予防のための生活習慣・体質改善~
日常生活での下痢・軟便の予防には、以下の点が挙げられます。
食生活の注意
- 冷たいものや刺激物、古いものや生ものを避けることが基本。
- 善玉菌の摂取:
ヨーグルト、納豆、発酵食品などで腸内の善玉菌を増やしましょう。市販の整腸剤を活用することも有効。 - 消化のよい食品選び:
おかゆ、煮込んだうどん、卵、鶏のささみ、白身魚、豆腐、バナナ、リンゴなどは腸への負担が少なくおすすめ。 - 食べ過ぎ・飲み過ぎの注意:
暴飲暴食、脂肪分の多い食品、刺激物(辛いもの、カフェイン、アルコール、炭酸飲料)は控えましょう。 - ストレス管理:
過敏性腸症候群はストレスと脳腸相関が深く関係。ストレスを溜め込まない努力や、ストレスへの対処法を身につけることが重要。受験生などはストレスが原因で下痢をする人も多いため、日頃から対策を意識しましょう。
規則正しい生活
- 生活習慣を規則正しく整えることも予防につながる。
- 規則正しい睡眠:
良質な睡眠が腸内環境の安定を促す。不規則な生活や睡眠不足は腸の働きに悪影響を与える。 - 適度な運動:
ウォーキングやストレッチなど、腸の蠕動運動を活発にする活動を普段から心がけましょう。体幹や腹筋を強化することも、排便力を高める助けに。
腸内環境の維持
- 腸内フローラ(腸内環境)を良好に保つことは、健康や生活に非常に大きな影響を及ぼす。
- 普段から整腸剤(市販薬のビオフェルミンなど)やヨーグルトを摂取するなどの対策が推奨されます。整腸剤には個人差があるため、ご自身に合うものを見つけるために何種類か試すことも有効。