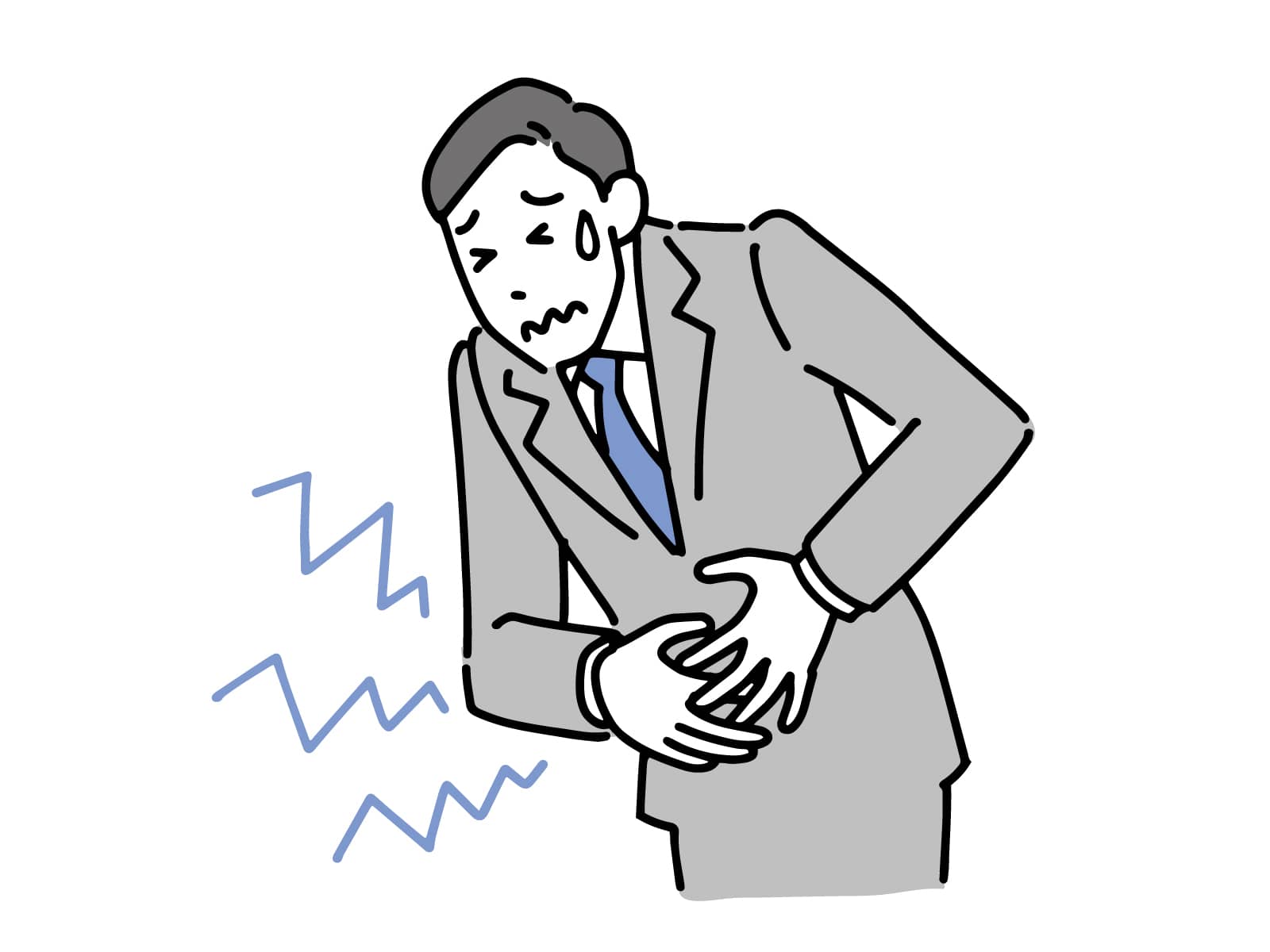 下痢や軟便は、多くの人が日常的に経験する消化器症状ですが、そのメカニズムや原因は多岐にわたり、適切な理解が重要です。
下痢や軟便は、多くの人が日常的に経験する消化器症状ですが、そのメカニズムや原因は多岐にわたり、適切な理解が重要です。
本記事では、下痢・軟便の定義から、その発生メカニズム、タイプ分類、原因、症状、病院で診察を受けるべき症状について詳しく解説します。
関連リンク
下痢・軟便の診断から治療・予防まで ~健やかな腸を目指して~
下痢・軟便の定義とは?
下痢:
便が通常よりも水分量が多く、形が整わない状態を指します。一般的に、1日の排便回数が3回以上、かつ便の水分含有量が約80%を超える場合を下痢と定義することが多いです。
成人では1日あたり200g以上の便量で定義されることもあります。ブリストルスケールでは、タイプ5〜7が軟便から水様便に該当し、下痢と判断されることが多いとされています。
軟便:
便の水分含有量が多くなり、形が保たれていても泥状となったり、崩れやすくなった便を指します。完全に水様ではなく、下痢の一歩手前の状態と見なされることもあります。
下痢のメカニズムについて
健康な状態では、小腸で消化吸収された残りの水分を大腸が適切に吸収し、適度な硬さの便が形成されますが、消化吸収過程で異常が生じると、大腸での水分吸収が不十分になり便の水分量が増加し、下痢につながります。
下痢を引き起こす主な生理的メカニズムは以下の4つに分類されます。これらが単独で、または複合的に作用して症状を引き起こします。
- 水分吸収の障害(吸収不良性下痢):
大腸が水分を正常に吸収できない状態。腸管そのものに炎症が起きて水分の吸収がうまくいかない場合や特定の薬剤などが原因となる。 - 水分分泌の促進(分泌性下痢):
腸管から過剰な水分や電解質が分泌される状態。細菌性毒素(コレラ菌など)や特定のホルモン、緩下剤などが原因となることがある。 - 腸管運動の亢進(運動亢進性下痢):
腸のぜん動運動が異常に活発になり、内容物が速く通過することで、水分吸収が不十分になる状態。過敏性腸症候群(IBS)や甲状腺機能亢進症、ストレスなどが主な原因として挙げられる。 - 浸透圧性下痢(浸透圧の増加):
腸管内に吸収されにくい物質が大量に存在することで浸透圧が高まり、体内から腸管内に水分が引き込まれる状態。乳糖不耐症や消化吸収不良、特定の緩下剤(マグネシウム製剤など)などが原因となる。
下痢・軟便のタイプ(分類)
下痢・軟便は持続期間、便の形状などの観点から分類されます。
持続期間による分類
- 急性下痢:
持続期間が通常2週間以内の下痢を指す。原因の多くはウイルス性胃腸炎、細菌性腸炎、食中毒、薬剤、急な食事内容の変化など。 - 持続性下痢:
2週間から4週間くらい続く下痢。一部の寄生虫感染や薬剤性などが原因となることがある。 - 慢性下痢:
持続期間が4週間以上続く下痢を指す。炎症性腸疾患、過敏性腸症候群(IBS)、薬剤性、吸収不良、内分泌疾患、悪性腫瘍など、多岐にわたる原因が考えられる。
便の形状による分類(ブリストル便形状スケール)
便の硬さや形状によって7段階に分類され、下痢傾向は特にタイプ5〜7が該当します。
- タイプ5:
やや柔らかい塊(軟便) - タイプ6:
どろどろ状(軟便~軽度下痢) - タイプ7:
水様便(下痢)
病態分類
前述の下痢のメカニズムと対応しており、吸収不良性下痢、分泌性下痢、浸透圧性下痢、運動性下痢に分類される。
下痢の主な原因(急性・慢性含む)
- 感染症:ウイルスや細菌による腸炎(例:ノロウイルス、サルモネラ、O-157など)、抗生物質使用後の偽膜性腸炎。
- 薬剤:抗生物質、抗がん剤、胃薬、人工甘味料、下剤などによる副作用。
- 飲食物:暴飲暴食、アルコール、脂っこい食事、乳糖不耐症、香辛料や冷たいものの過剰摂取。
- ストレス:精神的・身体的ストレスによる腸の機能異常。例:過敏性腸症候群(IBS)。
- 慢性疾患・炎症性疾患:潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患。
- その他の病気:虚血性大腸炎、腸結核、吸収不良症候群、甲状腺機能亢進症、ホルモン性腫瘍、がん、アレルギーなど。
下痢・軟便のおもな症状とは?
下痢・軟便の症状は、便の性状や排便回数の変化を中心に、以下のような特徴があります。
- 便の水分量が多い(軟らかい・水様便):
通常の形のある便に比べて、軟らかい、あるいはほぼ液体状の便が出る。 - 排便回数の増加:
1日に3回以上の排便が見られることが多く、特に感染性や刺激性の下痢では回数が多くなる。 - 腹痛・腹部不快感:
けいれん性の腹痛や下腹部の違和感を伴うことがある。 - 便意切迫感:
突然強い便意を感じ、すぐにトイレに行きたくなる状態。排便後もすっきりしないことがある。 - しぶり腹:
排便してもすっきりしない、何度もトイレに行きたくなる状態。 - ガスや腹鳴:
お腹がゴロゴロ鳴る、ガスがたまりやすいなどの症状。 - 発熱・嘔吐・倦怠感:
特にウイルス・細菌感染による急性下痢では、全身症状を伴うことがある。 - 血便・粘液便(炎症性腸疾患など):
潰瘍性大腸炎などでは血液や粘液を伴う便が出ることがある。
慢性的な下痢では、体重減少、栄養障害、脱水症状が問題となることもあります。症状の経過や便の形や状態を観察することが、原因の特定や適切な治療に役立ちます。
下痢や軟便 ~病院診察を受けるべき症状とは?~
下痢や軟便は、一時的な不調から重篤な疾患まで、その背景には様々な原因が潜んでいます。
症状が激しい場合、発熱や嘔吐を伴う場合、便に異常な色(血、黒、白)が見られる場合、しぶり腹がある場合、または2週間以上症状が続く場合など、気になる症状がある場合は自己判断せずに速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。
下痢・軟便で病院診察を受けるべき主な症状
- 重症または長引く症状:下痢が数日以上(通常3日以上)続く
- 1日に何度も水様便が出る
- 体重減少がある
- 発熱(38℃以上)を伴う
- 嘔吐が止まらない
- 血便や黒色便:便に血液や粘液が混じる。黒いタール状の便(消化管出血の可能性)
- 強い腹痛やけいれん:痛みで日常生活ができない場合や、触ると痛みが増す場合などは要注意。
- 脱水症状の兆候・口の渇き
- 尿量の減少
- 皮膚や唇の乾燥
- めまい・意識がぼんやりする
日常的な軽い軟便や一過性の下痢であれば経過観察でも問題ない場合が多いですが、上記のような症状がある場合は、重篤な原因が隠れていることもあるため、早めの受診が重要です。
とくに、過敏性腸症候群のように日常生活に支障をきたすストレス性の下痢の場合も、専門医に相談し、腸に器質的な病気がないか確認することをお勧めします。